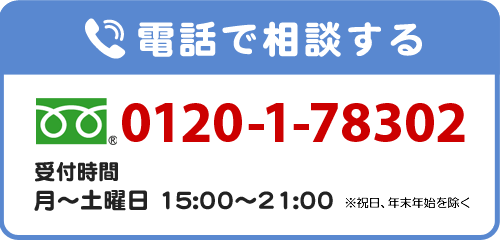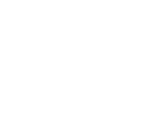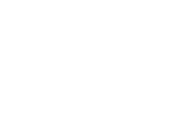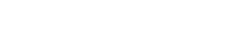相談事例
依存
相談内容(2016年6月・青少年女子)
通話ができるSNSアプリをダウンロードし、ユーザーとの通話で報酬を受け取れるサービスに登録をした。ユーザーから電話がかかってくると、それがランキングに反映され、ランキングが上がるとモチベーションが上がるので、続けていた。しかし、そのアプリに依存していたので、利用を止めようと思っているが、退会の方法がわからない。
アドバイス
アプリの利用規約により、退会にはパスワードの入力が必要である。パスワードがわからない、失くしたなどの状況であれば、運営会社にその旨を伝え、退会方法を問い合わせる必要がある。サービスを使う時は、自分自身の意思で登録しているはずであり、利用を停止するのも自分の意思である。利用を止めたいと思うならばその意思を運営会社に伝えてほしい。
ポイント
インターネットは「人から認められたい」、「人と繋がりたい」という人間の欲求を簡単に解決してくれるツールであり、簡単であるがゆえに依存状態に陥る側面があるだろう。膨大な人と繋がることでストレスを感じることもあるかもしれない。このように、インターネットに振り回されないために、何のために使うのかという「目的」、日常生活が乱れないよう「利用時間」を明確に決め、瞬時の満足感を求めるのではなく、自分の意思と責任でインターネットを動かし、便利に正しく使ってほしい。
相談内容(2016年1月・青少年男子の保護者)
スマートフォンを食事の時も離さない。学校に遅刻するようになり、成績も下がっている。最近、授業中にスマートフォンを使っているのが見つかり、没収された。没収されたスマートフォンは保護者が預かっているが、先生から、ルールを決めて本人に渡した方が良いと言われている。本人にルール決めさせているが、父親に却下されている。母親にのみ暴力もふるう。息子は、自由がほしいと言っている。ルールを作るのに何をしたら良いのか、息子に対してどう接すればいいのか。
アドバイス
ルールについては、このまま本人に決めさせるのが適切であり、さらに二重ルールにする。スマートフォンの利用に限らず、自由には責任が伴う。自由がほしければ、責任を持った行動が必要のはずである。まずは責任を持った行動として、生活態度の見直しが必要だろう。遅刻をせず学校へ行く、与えられた課題を期限どおりに提出する、先生や親との約束を守る。こうした行動をすることで、任せても大丈夫だと判断でき、自由も与えられるのではないだろうか。暴力については、110番、少年相談を勧める。警察は一般市民から見ると、怖くて敷居の高い存在かもしれないが、同じ過ちを繰り返してほしくない、正しく育ってほしいという強い思いで対応してくださるので、気軽に相談して良い。
ポイント
青少年のスマートフォンの所有は増え続けており、低年齢化、長時間利用の傾向も進んでいる。スマートフォンやインターネットを新たに利用する際には、長時間利用がもたらす日常生活への悪影響も親子で理解し、事前にルールを話し合うことが大事だろう。親子の信頼関係を損なわないためにも、ルール作りは必須である。すでに長時間利用が常態化してルールが守れない状態では、利用を止められることへの抵抗から、暴力に繋がるケースも少なくない。親子だけで解決しようとせずに、警察など公的機関の支援を受けることも有効だろう。
相談内容(2015年10月・青少年女子)
ネット依存気味である。勉強をしなくてはいけないと思いつつ、お風呂にもスマートフォンを持って行ってしまう。インターネットは、SNSの利用だけであり、アカウントを複数持っている。趣味、仲の良い友達との非公開のコミュニケーション、愚痴などで使い分けている。フォロー、フォロワーがたくさんいる。インターネットのことについて、親からは特別何も言われていないが、親の機嫌が悪い時、使いすぎだと言われる程度。成績も悪くない。
アドバイス
SNSのフォローが多ければ多いほど、タイムラインに流れてくる情報量は多くなり、自分に必要ではないものも混じっているだろう。フォローの人数を減らしたり、必要のないことは投稿しないなどで整理すると良い。インターネットは公共の場所であり、書き込んだ瞬間に自分の手を離れる。愚痴は電話や直接会ったときに話せば良く、いずれは無くしてほしい。自分に必要なもの、何を優先すべきかを良く考えて、行動に移してほしい。
ポイント
スマートフォンやインターネットの利用時間が長くなると、睡眠時間や勉強時間の減少などにつながり、体調不良や学力低下につながりやすい。自分がネット依存・スマホ依存かも知れないと感じたら、自分の1日のスケジュールをすべて記録してみると良い。インターネットやスマートフォンを利用している時間がどれぐらいかを正確に捉えることが改善への第一歩である。
相談内容(2014年11月・青少年女子の保護者)
子供に専用のPCを買い与えた。最初に「長い時間やらないように」と約束したが、最近は勉強している合間にダラダラとPCを使い、勉強との切り替えができていない。学校の授業の宿題で調べ物をしたり、音楽を聴いたりして使っている。就寝時間は決めており守られている。
アドバイス
最初にすべきこととして、子供の生活リズムを把握することが大事だろう。こたエールのホームページに公開している「睡眠&生活チェックシート」を使って、一定期間を決めて記録すると良い。子供本人も自分の時間の使い方が見えてくる。「何時間勉強して何分休み」というルールを親子で話し合って決められるだろう。ルールが決まったら紙に書いて張り出すことで意識させると同時に、守れなかった場合の罰則も親子で話し合って決めると良い。一度ルールが決まったら、それが守られているかをチェックする必要がある。揺るぎない姿勢を見せることも子供にとって大事である。
ポイント
子供と話し合って決めたPCやインターネットの利用ルールは、作って終わりではなく、子供がルールを守れているか、常に親自身も関心を持って見守り、チェックし、支援する必要があるだろう。親の目を子供が意識すれば、自分が約束を守らなければと感じ、ルールが守りにくければ不満をぶつけてくるだろう。親への不満は、子供と話す絶好のチャンスだと捉えたい。この会話のキャッチボールが親子の関係性をより良い方向へ導く方法であり、どんな発言であっても「まず聴く」姿勢が親に求められていることを忘れてはならない。
相談内容(2014年10月・青少年男子の保護者)
スマホは親が息子に貸し出す形で使わせているが、夜9時には返す約束をしている。このため9時まではスマホを手放さない。9時を過ぎると、自分で購入したゲーム機で夜中まで遊んでいるようだ。お風呂に入らないこともある。利用ルールは何度も話し合い作ったが、守れない。取り上げようとすると反抗的になる。こういう状況で、無理やり取り上げたほうが良いのか、取り上げないほうが良いのか悩む。
アドバイス
ゲームをすること自体は悪いことではないが、健康被害や学業への影響が問題であることを本人に気づいてもらいたいので、ゲームの楽しみへの理解を示しつつ、再度、その付き合い方を話し合えると良い。最低限守ってほしい日常生活の約束事を設け、日常生活を続けるための利用ルールを息子さん自身に考えてもらい、ペナルティも本人に決めてもらうと良い。本人に考えてもらうことが大事である。こたエールのホームページに公開している「睡眠&生活チェックシート」も利用することを勧める。
ポイント
ゲーム依存は、長時間ゲームに没頭することで、日常生活や健康に支障が生じることが一番の問題である。ゲームに没頭するあまり、本来やるべきことを見失っていないか、本人が意識し、ゲームとの付き合い方をコントロールできることが望ましい。端末にフィルタリング、機能制限、時間制限などを導入することも有効である。一方、依存の背景には、学校での友達関係、家庭環境、思春期の悩みなど、子供がストレスを抱えているケースも多く見られる。改善が困難な場合は専門外来に相談することも大事だろう。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。