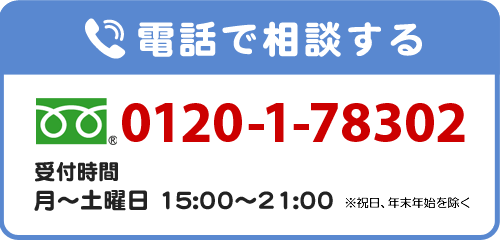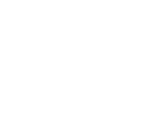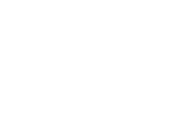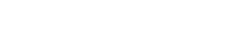相談事例
依存
相談内容(2025年12月・青少年男子の保護者)
子供のゲーム依存がひどく、学校も行けたり行けなかったりの状態が続いている。時間を守らせるためにゲーム機を預かっていたが、最近はゲームをさせてくれないと学校に行かないと言って暴れるため、落ち着かせるためにゲーム機を返してしまう。日常会話はできるが、ルールに関する話がまったくできず困っている。
アドバイス
保護者にできる大切なことは、終了時間のルールを決めて守らせることと、フィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)によって機械的に時間を制限することである。ただし暴れるなどで家庭での解決が難しい状況になってしまったときには、家族だけで抱えずに外部の機関にも相談してほしい。ゲームについては「ゲーム障害」という病名で治療が始まっているので、自分の意志で止められない状況であれば、専門医を受診することが勧められている。
ポイント
子供を落ち着かせるためにゲーム機を返すことが効果的な場合もあるかもしれないが、結果的に依存を助長させている可能性もあるため注意が必要である。緊急切迫性のあるトラブルに関しては110番だが、ためらわれる場合は、警察には青少年とその保護者向けの相談窓口もあるため、事前に相談し不安を解消しておくのも選択肢だろう。
相談内容(2025年8月・青少年男子の保護者)
息子が何年も前からゲームに夢中で、夏休み中も1日中ゲームをしている。インターネットを切断したり、端末に制限をかけたりしているが、最近は暴力的になり家族への影響も心配している。学校では注意されるとやめるようだが、家庭ではうまくいかずルールを守らせることが難しい。
アドバイス
子供にとってはゲームは学びの場にもなり得るため、ゲーム自体を否定するのではなく、長時間利用による生活リズムの乱れや睡眠不足といった具体的な影響について、丁寧に伝えられると良い。そのうえで、再度親子で話し合ってルールを見直すことや、守れなかったときのルールを決めておくことが大切である。さらに親子で話し合ったルールに基づいてフィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)を利用して時間を制限することも勧める。家庭内で対応が難しい状況に陥った場合には、外部の専門機関にも相談してほしい。
ポイント
夏休み期間中は、インターネットやゲームの長時間利用によって日常生活、勉強、健康に支障が出たり、家族関係が悪化するなどの相談が増える傾向がある。基本的な対策は、家庭でのルール作りとフィルタリングなど機械的な制限の利用だが、保護者だけでは対応しきれないケースも少なくない。特にゲーム依存(正式な呼び方は「ゲーム障害」)は治療が必要な疾患として正式に認定されており、家庭内だけで抱え込んでしまうと問題が深刻化することもある。保護者の精神的な負担を軽くするためにも、外部の支援機関のサポートを受けることも大事である。
相談内容(2025年4月・青少年男子の保護者)
学校から配布されたタブレットでゲームをやり始め、最初は時間制限を守っていたが、今は何度も時間を延長し延々とやっている。注意をしてもやめず、暴れるなどしてルールを守らせるのが難しい。
アドバイス
学習端末が本来の目的から外れて遊び道具に使われているとしたら、利用目的や利用時間の見直しが必要だろう。保護者ができる対策として、タブレットの利用時間や利用できるサービスを機械的に制限することを勧める。何のアプリにどのくらい時間を使っているのか特定できているのであれば、ブロックをすることで物理的に使えないようにすることも可能である。生活リズムの悪化、睡眠不足、視力低下など、長時間利用の影響を丁寧に伝えてみるのも良い。ただし学校配布の端末のため、制限できる範囲については学校に相談するのが良いだろう。制限が難しいようであれば、学校や保護者に預けるなどで工夫ができると良い。
ポイント
ゲーム、SNS、動画視聴などで貴重な時間を使い過ぎないためのルール決めのポイントは、子供本人に主体的に考えてもらうことと、守られなかったときのルールについても話し合って決めておくことである。ルールを守りやすくする仕組みがフィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)であり、アプリごとに時間を制限することもできるので活用してほしい。学校から配布された端末の設定変更を保護者側ではできない場合は、Wi-Fiルーター用のフィルタリングで利用できるサービスを制限したり、利用できる時間を設定することも対策の1つである。
相談内容(2024年11月・青少年男子の保護者)
息子のインターネットやゲームの利用時間が長いのだが、適切な利用時間はどのくらいなのか。通話アプリで複数の友人と話しながら何時間もゲームをしており、食事や入浴の声をかけても止めず生活が乱れている。夜も利用できる時間のルールを決めているが、すぐに止められずに延ばされる。
アドバイス
インターネットやゲームの適切な利用時間は各家庭に委ねられているが、大切なことは、終了時間のルールを守ることや、生活習慣がおろそかにならないようにすることである。家族全員でルールを話し合って決め、守れなかったときのルールも同時に決めることを勧める。フィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)によって機械的に時間を制限することも検討してほしい。特にフィルタリングについては、保護者が希望しない場合を除き、子供の端末に設定することが法律で義務付けられているので利用してほしい。
ポイント
長時間のゲームで日常生活や勉強に支障が出ていたり、心身の健康を損ねていたり、家族関係が悪化しているという相談はとても多い。状況が深刻化する前に保護者にできる対策は、親子で利用ルールや1日の過ごし方を見直すことと、フィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)を導入することである。冬休みなど長期の休み中に生活リズムを崩さないよう、休みに入る前に、スマートフォン、インターネット、ゲームとの付き合い方の見直しができると良い。
相談内容(2024年6月・青少年男子の保護者)
息子がスマートフォンを手離さず、ゲーム中心の生活になっている。時間制限の機能を利用しているが、使えない時間になると暴力的になり制限を解除してほしいと要求する。制限を解除する代わりに自分で時間を管理する約束をしたが、結局、ゲームを優先してしまい、やるべきことができなくなっている。
アドバイス
フィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)によって機械的に時間を制限するのが適切な管理方法であるため、これからも続けてほしい。スマートフォンやゲームに振り回されないために、1日24時間をどのように過ごすのかを親子で話し合いながら、利用ルールを本人に決めてもらうことを勧める。こたエールホームページに掲載の「睡眠&生活チェックシート」も参考にしてほしい。家庭だけでは解決が難しいと感じるようであれば、医療機関に相談することを勧める。
ポイント
スマートフォンやインターネットが生活に不可欠な道具であると同時に、子供は長時間利用の影響を受けやすく、 特にゲーム依存は低年齢化が懸念されている(「ゲーム障害」という疾病として世界保健機関(WHO)によって認定されている)。このため保護者の適切な見守りは必要であり、フィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)の役割も大きい。子供と対話をしながら、使って良い時間や場所、アプリについて親子で合意をとりながら、機械による制限を活用して予防につなげることが大事である。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。