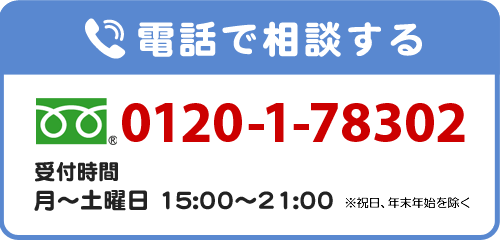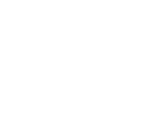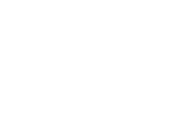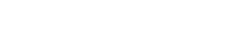相談事例
取引トラブル
相談内容(2026年1月・青少年女子)
グッズ取引相手の保護者を名乗る人から「数年前の取引で、代金を支払ったがグッズが届いていない。発送しないと警察に相談する」と書かれた手紙が届いた。自分は売る側で取引をしていたが、SNS名など取引の詳細は書かれておらず、グッズ取引で利用している決済アプリの履歴を見ても手紙に書かれた日の取引は確認できなかった。身に覚えがないので嘘かもしれないが対応に困っている。
アドバイス
身に覚えがないならば、手紙に書かれている内容が嘘である可能性も考えられる。取引をしていた当時の履歴(SNS名、相手のアカウント名など)をもう一度確認してほしい。どうしても確信が持てないようであれば、一人で相手とやり取りをせず、保護者への相談を勧める。手紙が届いていることから相手に住所や名前などの個人情報を知られているため、社会経験の豊富な保護者や身近にいる信用できる大人の力を借りてほしい。
ポイント
グッズ交換のように青少年が集まりやすい場所では、未熟な青少年を狙っている人もいるかもしれないので注意してほしい。また、SNSを介したグッズの取引の場合、そこでトラブルになってもSNS側の支援は得られず、自己責任で解決しなければいけないことも多い。売りたいものがあったとしても、安易にSNS等での取引は避けること。なお、大手のフリマアプリでは匿名での発送も可能であることから、今回のようなトラブルは起きにくいと思われる。また、商品到着の通知後に、販売者に代金が支払われる仕組みとなっており、料金トラブルが起きにくいものの、到着前や届いた商品に納得する前に「評価」をすると、代金だけ支払われて出品者と連絡が取れなくなるケースもあるなど「個人間取引」にはリスクがあることを十分に理解し、利用規約をよく理解して、慎重に取引を行ってほしい。
相談内容(2025年7月・青少年女子)
SNSで知り合った人と一緒にアイドルのコンサートに行く予定だったが、急に音信不通になり、結局行けなくなったという連絡があった。チケット代を立て替えていたので、その後もメッセージを送り続けていたが、既読無視をされたり曖昧な返事しかしてもらえず、最後は完全にブロックされてしまった。
アドバイス
チケット代を支払ってもらうためにも、保護者や信頼できる人から電話やショートメールを送ってもらうことを勧める。相手から反応がなかったとしても、連絡を取ろうとすることは大事であり、今後のためにも履歴を残しておくと良い。これまでのやり取りも消さずにスクリーンショットなどに保存しておくことを勧める。進展がなく解決が難しいようであれば、弁護士に相談するなど法的な解決方法を検討することも選択肢の1つである。
ポイント
SNSを通じて趣味が合う人と出会うのは楽しい一方で、お金が関わるやり取りをするときには慎重になる必要がある。SNS上のつながりでは、現実の友達関係とは違い、相手のことを深く知ることができず、トラブルになったときに解決が難しくなってしまうこともよくあり、この事例のようなチケットの取引に関するトラブルも増えている。チケットが余ったときには、主催者が案内している公式のリセールサービスなど、安心・安全に利用できる方法を選んでほしい。
相談内容(2025年2月・青少年男子)
SNSでスポーツ観戦チケットを売っていた人から購入しようとしたところ、相手からメッセージアプリでのやり取りを指定され、決済アプリで先に代金を送金した。しかしチケットを受け取れないままブロックされ、相手と連絡が取れなくなった。
アドバイス
金銭被害が出ているので早めに警察へ相談してほしい。相談するにあたり、相手について知っている情報、やり取りの内容、送金画面など、証拠となる情報は消さずにスクリーンショットに保存しておくと良い。また、決済アプリ会社にも連絡をして、支払ったお金について対策があるのか相談してほしい。相手に教えた自分の情報についても整理し、不審なDMや友達申請などが届いた場合に備えておくと良い。
ポイント
SNS上で人気のチケットを欲しがっている人を狙った詐欺が多発している。送金には決済アプリが使われることも多く、お金のやり取りが簡単にできることで青少年もトラブルに巻き込まれやすくなっている。インターネット上では相手の素性や信用できる人かどうかを見抜くのが難しいことをよく理解し、安易に取引に応じないことが大事である。チケットを買う場合も、余ってしまい譲渡したい場合も、必ず主催者やチケット販売会社が認めている公式の方法を確認してほしい。仮にチケットを入手できたとしても、公式で入手したチケット以外は入場を認められない可能性や、偽造チケットだったために入場を拒否される可能性もあるので注意してほしい。
相談内容(2024年9月・青少年男子)
SNSでゲームアカウントを安く売っている人を見つけ、メッセージを送り、決済アプリで先にお金を支払った。すると、他にも欲しがっている人がいると言われ、値上げを要求された。しかし無理だったので断ると、ブロックされて連絡が取れなくなった。
アドバイス
相手にブロックされている状態だとしても、SNSのアカウントがまだ残っているなら、消されないうちにユーザー名などわかっている情報を書き留めておくと良い。保護者に協力してもらい、SNSのダイレクトメッセージで連絡を取ってみることも1つの方法だろう。それでも相手が返金に応じない場合や、詐欺だと考えられるときには警察に相談することもできるだろう。一方で、アカウントを買う行為も規約違反としてゲーム会社から厳しい措置を取られる可能性もある。今後はルールを守って安全に利用してほしい。
ポイント
SNSを利用した個人の取引は安全に成立するケースばかりとは限らず、お金を取られてしまうトラブルが多発している。アプリによる支払いも手軽になり、欲しいものが簡単に手に入るのは魅力的かもしれないが、だまそうとしている人がインターネット上にはたくさんいることを理解し、安易に買おうとすることは避けてほしい。ゲームのアカウントやアイテムの売買に関しては、リアルマネートレーディング(RMT)と呼ばれ、多くのゲーム会社が禁止していることも忘れてはならない。
相談内容(2024年4月・青少年女子)
友達から中古品を買い取ってほしいとSNSを通じて持ちかけられ、自分が先にスマートフォンの決済アプリを利用して送金した。友達からは品物を送ったと連絡があったが数日経っても届かなかった。何度か催促したが曖昧にされており、送るつもりがないのにお金だけ送金させたのではないかと疑い始めている。その友達とは今はSNSだけの繋がりなので対処に困っている。
アドバイス
解決に向けてできることは、相手に発送や返金に応じてもらえるように根気強く連絡を取り続けることだろう。その際、連絡した日時や内容は記録しておくと良い。SNS以外の連絡手段も探してみて、電話やメール、郵便などで連絡をすることも検討してほしい。保護者にも相談して一緒に対応してもらうことも勧める。
ポイント
お互いによく知っている友達関係では、インターネット上でトラブルになっても話し合いで解決できることも多い。特にお金に関する問題は、時間はかかるかもしれないが、約束が果たされるように実際に会って話し合う機会を作ることが大事である。SNSやキャッシュレス決済アプリは、青少年にとっても日常的な道具となっている反面、特に個人同士で金品のやり取りに使うときにはリスクもある。慎重に行動しなければならない場面がたくさんあることを理解しながら利用することが大切である。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。