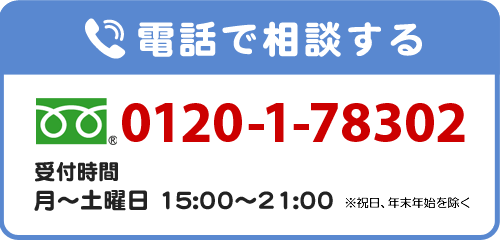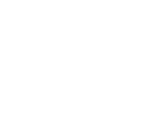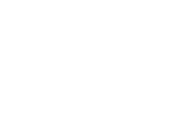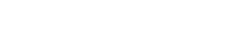相談事例
情報セキュリティ
相談内容(2025年10月・青少年男子)
学校でスマートフォンを机に置いたまま席を離れ戻ったところ、自分では開いた覚えがないのにスマートフォンの設定画面が開いていた。スマートフォンを盗み見られたり、操作をされていたかもしれず、確認する方法を教えてほしい。
アドバイス
どのような操作をされたのかを確実に調べることは難しく、誰も操作していない可能性もある。できる範囲の確認方法として、見覚えのないアプリが入っていないかを調べたり、メールの送受信履歴やブラウザの閲覧履歴、利用しているSNSの投稿などを確認することを勧める。大切なスマートフォンを安心・安全に使うために、今後は画面ロックを設定しておくとともに、離席する際、貴重品は携行すると良いだろう。学校でスマートフォンの管理方針が決まっていれば、その方針に基づいた管理をすることも勧める。
ポイント
スマートフォン、ノートPC、タブレットなどを学校や外出先で利用する機会も増えてきており、安全対策が不可欠である。身に覚えのないアプリが入っていないか、メールの送受信履歴、SNSの履歴などを日頃からチェックしておくことが大事である。端末の初期化(工場出荷状態に戻す)を行えば、不正なアプリなどをダウンロードされていたとしても削除されるが、端末内の情報を盗み見されていた場合は、初期化をしても一度相手が知った情報を取り戻すことはできない。後から不安にならないためにも、画面ロックが早くかかるように設定しておくことも大事な対策である。
相談内容(2025年1月・青少年女子)
SNSのアカウントが乗っ取られパスワードが変更されてしまい、自分ではログインできなくなってしまった。アカウントは非公開で一切投稿していなかったのに、保存していた動画が公開されてしまっている。プライベートな内容なので知られたくない。
アドバイス
パスワードが変えられていることから、SNSに用意されているパスワードリセットの手順を試してみることを勧める。ヘルプページに書かれている内容をよく読み、現在の状況と照らし合わせて対応してほしい。問題が解決しない場合は、運営会社へ直接問い合わせる方法もある。他人のSNSに不正にログインする行為は不正アクセス禁止法という法律に抵触している可能性がある。実際に被害も生じているので警察にも相談をしてほしい。
ポイント
SNSの利用で気を付けたいトラブルの1つが不正アクセスである。SNSの投稿が書き換えられたり、非公開にしていた情報が流出してしまうほか、フォロー/フォロワーに偽のメッセージが送信されてその人たちからも情報を収集するなど、被害が拡大してしまうケースもある。トラブルのきっかけはパスワード流出が考えられるため、パスワードは日頃から大切に管理することと、二段階認証や生態認証などパスワード以外の認証方法も設定しておくとより安全である。
相談内容(2024年5月・青少年女子)
自分のSNSに誰かが不正にアクセスし、友達と勝手にダイレクトメッセージ(DM)のやり取りをしていた。自分になりすました人物が、友達に迷惑行為をするように促していた。パスワードを変えたので被害は収まり、誰の仕業か予想もついているが、確実に相手を特定したい。
アドバイス
不正にアクセスされ実際に被害も起きているようなら、法律違反の可能性もあるため、DMのやり取りなど証拠を持って管轄の警察署に相談してほしい。SNSのアカウントについては、パスワードを推測できないような複雑なものにすぐに変更し、SNS上で相手とやり取りをしてしまった友達とは、直接話をして誤解を解けると良いだろう。
ポイント
SNSの不正アクセス、乗っ取りのトラブルの多くは、パスワードを知られないように対策することで未然に防ぐことができる。パスワードを他人に教えないことがもっとも重要だが、自分の名前と誕生日の組み合わせのようなパスワードは、SNSのプロフィールなどから推測されやすいため注意が必要である。1つのパスワードを複数のサービスでも使い回さないことや、二段階認証を利用することも有効である。自分のアカウントが不正にアクセスされていることがわかったら、早急にパスワードを変更して被害を食い止めることが大事である。
相談内容(2023年11月・青少年男子の保護者)
息子のゲームアカウントが他人に乗っ取られてしまったようだ。息子はパスワードなどアカウントに関する情報は誰にも教えていないと言っているが、パスワードは簡単に推測できるものだったとわかった。すでにパスワードを変更されてしまいログインができず、犯罪などに巻き込まれないか心配である。
アドバイス
アカウントを取り戻せるように運営会社へ問い合わせをすることを勧める。アカウント名、登録情報、ログインができなくなった日時、画面のスクリーンショットなどを問い合わせの前に整理して保管しておくと良いだろう。また、他人にパスワードを教えたことがないのに乗っ取られたのであれば不正アクセスをされた可能性もあるため、被害が大きくなるのを防ぐためにも警察に相談することを勧める。アカウントを取り戻したら、同じトラブルが起きないようにパスワードについて家族で話し合えると良い。
ポイント
アカウントが乗っ取られてしまう主な原因はパスワードが知られてしまうことである。たとえ自分からは教えていなくても推測されてしまうケースも多く、単純な数字や辞書に載っているような単語、名前や誕生日を使ったパスワードは危険だと考えたほうが良い。また、同じパスワードを複数のサービスでも使い回していると、1つのパスワードが知られた場合に別のサービスも狙われやすくなってしまうため注意が必要である。パスワードも個人情報の1つであり、自分自身で大切に守っていけるように親子で話し合えると良いだろう。
相談内容(2023年9月・青少年性別不明)
インターネットで検索をしていたら、スマートフォンがウイルスに感染している可能性があるというメッセージが出たので、画面を一度閉じて開き直したらメッセージが消えていた。スマートフォンは問題なく使えているので偽のメッセージだったのかもしれないが、どうしたら良いか。
アドバイス
インターネットの画面上でウイルス感染の文字が表示されただけだとすると、見た人を焦らせるような偽のメッセージかもしれない。このため、画面のメッセージに反応したり、何か情報を求められても入力をしてはいけない。スマートフォンのソフトウエアが最新状態になっていることを確認し、セキュリティソフトを利用しているのであれば念のためウイルスチェックをしておくと安心である。
ポイント
インターネットを見ているときにブラウザ画面にウイルス感染の警告が表示されたとしても、実際に感染しているのではなく、 「偽警告」、「フェイクアラート」と呼ばれる偽物のメッセージの可能性がある。この場合はメッセージに誘導されて何かをインストールしたり、個人情報を入力することで本当のトラブルへと発展してしまうため、焦らずにブラウザやウインドウを閉じることが一番安全な対処だと考えてほしい。もしも本物の警告だった場合は、利用中の正規のセキュリティソフトの手順通りに解決していくことになるが、一人で判断せずに保護者に相談して対処してもらうことが大切である。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。