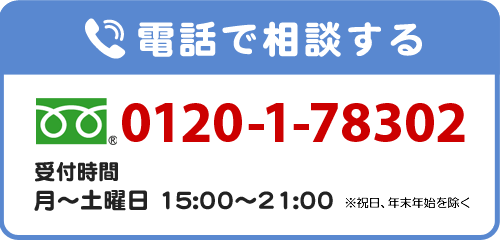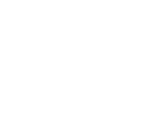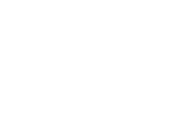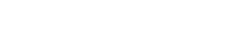相談事例
ネットいじめ
相談内容(2025年12月・青少年男子)
友人と一緒に参加しているグループチャットで、あまり仲良くない知り合いが自分の名前を出して「死ね」と投稿した。この投稿に対して開示請求、賠償請求ができるのだろうか。
アドバイス
開示請求とは、誹謗中傷などを行っているアカウントの発信者情報を明らかにするための手続きであり、今回は相手の素性がすでに分かっているため、まずは本人に直接注意したり、友人から注意してもらうことを勧める。本人同士の話し合いで、投稿を消してもらったり、同じことを繰り返さないことを約束してもらったうえで和解できるのが理想である。しかし、人権を侵害するような発言など、言ってはいけない言葉もある。法的な解決を望むようであれば、弁護士や法律の相談ができる窓口へ相談してみることを勧める。
ポイント
インターネット上で悪口を言われた場合、開示請求(発信者が不明の場合)や、損害賠償請求も選択肢であり、実際に損害賠償請求が認められた例も増えている。一方でこうした手続きには弁護士など専門家のサポートが必要であり、費用や手間もかかる。未成年の場合は保護者の協力も欠かせない。また、請求は必ず認められるわけではなく、裁判所の判断になる点も注意が必要である。悪口を言われたら腹が立つのは当然のことであるため、気持ちの整理で解決するのか、法的な対応も視野に入れるのかなど、今はインターネットの誹謗中傷に関して相談できる窓口も増えているため、相談しながら納得できる方法を見つけられると良い。
相談内容(2025年8月・青少年女子)
動画投稿をしているが、アンチコメントが削除しても書き込まれるため、どう対応したら良いか。動画投稿アプリのアカウントは自分のもの。保護者は動画投稿をしていることは知っているが、アンチコメントが書き込まれていることは知らない。
アドバイス
嫌なコメントであっても過剰に反応しないことがトラブルを大きくしないコツであり、削除をしたのは正しい対応である。削除以外には、相手をブロックしたり、コメントを非表示にする方法もあり、利用規約で禁止されているような内容であれば運営会社に違反報告をすることもできる。どのような対応が良いか、保護者にも相談して一緒に検討することを勧める。コメントをきっかけにいじめや誹謗中傷に発展しないように、自分自身も利用規約をよく読み、ルールを守って安全に利用してほしい。
ポイント
動画投稿サイトはコメントやメッセージを通じて他者と交流ができる一種のSNSである。動画をきっかけに人と親しくなることもあるが、顔が見えないコミュニケーションでは、相手を傷つけるようなコメントが投稿されることも残念ながらある。悪質なコメントの投稿はルールに反する行為だが、インターネット上では相手の行為をすぐに止めることが難しい。このため、このようなリスクがあることもよく理解し、被害者にならないための対処法を知っておくことが大事である。安心して利用するためにも、インターネット上のマナーや安全な使い方を身につけてほしい。
相談内容(2025年6月・青少年女子の保護者)
娘が同級生女子からSNSで誹謗中傷を受けている。相手とは元々は仲が良かったが、娘が付き合い方に悩んでいると、SNSを使って誹謗中傷のメッセージを送ってくるようになった。別の友達にも娘の悪口を言ったり、娘の写真を悪意のある形で送っている。
アドバイス
誹謗中傷については、使われた言葉や頻度が分かるよう、スクリーンショットに保存しておくと良い。送られた写真は、受け取った人に削除をお願いする必要があるため、信頼できる友達にも協力を頼めると良い。相手との関係を踏まえ、本人同士で話し合えるのが理想的だが、状況によっては学校の先生にも相談して適切に指導をしてもらうことも必要かもしれない。SNSでのトラブルであっても学校生活に影響が出ている場合は、本人の気持ちを何よりも尊重した上で、いじめ問題として学校での適切な対応が望まれる。
ポイント
SNSでの誹謗中傷に対しては、ブロックや通知をオフにするなどで距離をおく対応が有効である。しかし、相手がリアルの友達の場合は、人間関係や学校生活を含めた根本的な解決が必要になる。SNSの中でのトラブルは保護者には見えにくく、子供が相談をためらうこともあるが、放置すると深刻化する恐れがあるため、保護者が日頃の会話を通じて様子を把握し、適切に支援することが大切である。
相談内容(2025年3月・青少年男子)
SNSに部活のグループがあり、そこに自分が写った写真が加工されて晒されていた。過去にも別のメッセージアプリで同じことをされたので先生に指導してもらったが、また再発した。傍観するメンバーもいる。
アドバイス
本人の許可なく容姿の写真を加工し、インターネットで公開することは、肖像権やプライバシー権の侵害にあたる可能性がある。載せている人が身近な知り合いのため、直接削除をお願いすることが一つの方法であるが、相手が削除に応じない場合や、直接お願いすることが難しい場合は、SNS運営会社への通報も考えられる。さらに、SNS上のトラブルだったとしても学校の生徒同士で起こった問題であるため、学校の先生にも相談を続けてほしい。 今後の対処で必要になる場合に備えて、載せられた写真は証拠としてスクリーンショットなどに保存して残しておくと良い。
ポイント
デジタル写真は電子データのためコピーや編集が簡単であり、さらに生成AIや画像加工機能によって専門知識がなくても手軽に編集ができるようになったため、このようなトラブルが増えている。他人の写真を本人の許可なく加工したり公開することは、人の権利を侵害する行為であり、法律の点からも許されないことである。便利な機能をいじめや悪ふざけの道具にしないこと、インターネットは公の場であることを理解し、正しく安全に利用することが大切である。
相談内容(2024年11月・青少年女子)
SNSで、ある人の名誉を傷つける投稿とそのコメント欄が盛り上がっているのを見て不快になったので、投稿している人の中で自分と関わりのある人をブロックした。するとブロックした人からアカウントを変えてメッセージが届き、ブロックした理由を聞かれたので説明したが、そのときの自分の発言が誹謗中傷に該当していたかもしれない。
アドバイス
誹謗中傷かどうかは、発言自体のほかに経緯なども含めて総合的に判断されるため、心配であれば法律専門の窓口や弁護士に相談することを勧める。しかし大事なことは、状況を悪化させないことであり、お互いに対話をして和解できるのが一番良い。文字でのやり取りではお互いに真意を伝え合うことはとても難しいため、トラブルになったときにも常に冷静な態度で正しい言葉を使うようにしてほしい。
ポイント
インターネット上での発言は文字として残ることを意識し、どのような状況でも送信前に一度立ち止まって考える習慣をつけると良いだろう。匿名での会話だったとしても、相手を不快にさせる発言をしてしまった場合は、丁寧に謝罪をすることが大切であり、トラブルを大きくしないコツである。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。