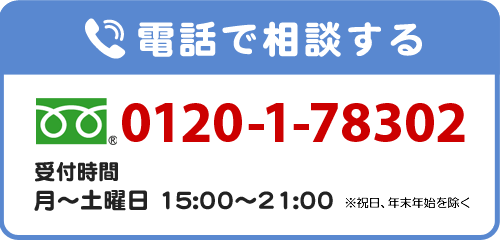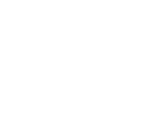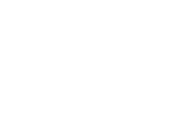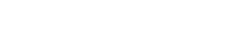相談事例
有害情報
相談内容(2026年1月・青少年女子)
18歳未満だが、アダルトサイトに入り「18歳以上ですか」という質問に「はい」と答えて閲覧してしまった。サイト内のコンテンツのダウンロードはしていない。この行動は罪に問われるのだろうか。
アドバイス
アダルトコンテンツを見ること自体は違法ではないが、年齢を偽ってサービスを利用することは、各サイトの規約違反にあたる。規約違反が直ちに犯罪となるわけではないが、トラブルを避けるために必ず守る必要がある。特にアダルトサイトではワンクリック請求のように不正にお金を請求されるトラブルも多く起きているため、自分自身を守るためにも、各サイトの利用規約を必ず確認し、ルールを守って利用してほしい。
ポイント
インターネット上では年齢を偽ることもできてしまうが、年齢制限のあるコンテンツは、その制限が設けられている理由があることを理解し、サイトの規約を守ることが大切である。この事例ではサイト内のコンテンツをダウンロードしていなかったが、児童ポルノなど違法性のあるコンテンツをダウンロードしてしまうと、法律違反につながる可能性もある。なお、アダルトサイトに限らず、ゲームやSNSなどのアプリにも利用規約があるため、安全な利用のためによく使っているサービスの利用規約は確認しておくと良い。
相談内容(2025年9月・青少年男子の保護者)
子供のスマートフォンを操作し検索履歴を見たところ、卑猥な言葉で検索をしており驚いた。子供のスマートフォンにはペアレンタルコントロールの機能を設定したと思う。機械に疎いので購入店で設定してもらったが、詳しいことはわからない。
アドバイス
フィルタリングやペアレンタルコントロールでは子供のスマートフォンを直に操作をしなくても、保護者側の管理画面からも子供の検索履歴など利用状況の確認ができるので、今後も見守りを続けてほしい。一方で思春期の子供が性に関心を持つこと自体は自然なことであり、性について子供、保護者が相談できる窓口へ相談することも勧める。
ポイント
子供がインターネット上の有害情報にアクセスしないよう、保護者側が安全な環境を整えることが大切である。保護者に活用してほしい機能として、「フィルタリング」と「ペアレンタルコントロール」の2つがある。「フィルタリング」はインターネット上のウェブサイトやアプリなどを一定の基準により選別し、青少年が有害な情報を閲覧できないようにする機能であり、「ペアレンタルコントロール」はスマートフォンの利用時間など、利用を制限、管理できる機能である。その他、インターネット検索時に不適切なコンテンツをブロックする「セーフサーチ機能」も有効である。このような対策をした上で子供にスマートフォンを渡すのが望ましいが、どのような制御がされているのかを保護者自身が理解することも大切である。
相談内容(2025年2月・青少年女子の保護者)
娘が使っている家族共有のタブレットで動画アプリを開くと、おすすめ動画にアダルト動画が出てきた。娘がそのような動画を見たのか疑問だが、今後表示されないためにはどうしたら良いか。
アドバイス
「おすすめ」は、利用者それぞれの検索や閲覧などの傾向を元に選ばれて表示される仕組みである。今後、同じような動画が表示されないように、アプリに残っている検索や閲覧の履歴は消去しておくと良い。動画の内容がサイトの規約に違反した内容であれば、違反報告をすることも有効である。さらに、家族共有の端末であっても、アダルト動画をはじめ有害なコンテンツから子供を守るために、制限をかけておくとより安全である。
ポイント
子供に見せたくないコンテンツのブロックにはフィルタリングが有効だが、利用を許可しているSNSなど個々のサービス内においても、保護者向けの機能や、セーフサーチ機能を活用し、不適切な情報に子供が接しないようにうまくコントロールできると良い。おすすめを表示する機能(レコメンド機能と呼ばれる)については、便利な面もあるが、興味のあるコンテンツが次々と流れてくるため閲覧時間が長くなったり、閲覧する情報が偏るなど、青少年にとっては良い面ばかりではないので注意が必要である。
相談内容(2024年6月・青少年男子)
未成年なのに成人向けのコミックをインターネットで買ってしまった。このことをQ&Aサイトで調べたところ、いけないことだと書いてあったので家族に迷惑をかけてしまうのではないかと不安になった。
アドバイス
年齢を偽って購入したのであれば、販売サイトの規約違反にあたるかもしれないので注意してほしい。トラブルや不安を解消するために、できれば今回の件を保護者にも話して、一緒に対処してもらうことを勧める。成人向けのサイトやコンテンツでは、悪意のある事業者から不当にお金を請求されるトラブルもあるため、利用年齢に達していないサイトへは近づかず、規約を守って利用してほしい。
ポイント
青少年にとって有害な図書類を未成年者に販売することは、法律や条例に基づいて規制されており、販売サイトにおいても未成年者の閲覧や購入が禁止されていることがある。インターネット上では年齢を偽ることもできてしまうが、年齢制限のあるコンテンツは、その制限が設けられている理由があることを理解し、サイトの規約を守ることが大切である。
相談内容(2023年12月・青少年女子の保護者)
外出先で子供にスマートフォンを貸してほしいと言われ、貸したまま目を離してしまい、その間に子供がアダルトコンテンツを見てしまったようだ。アクセス履歴を見るとゲーム攻略サイトにアクセスしていたが、そのサイトにはアダルト広告がたくさん表示されていた。
アドバイス
今後も不適切なコンテンツを子供が見ないように、フィルタリングなどのペアレンタルコントロール(機能制限)の利用を勧める。特にフィルタリングは法律上も、子供が利用するインターネット端末で利用することが決められている。保護者のスマートフォンであっても、子供に貸している間はフィルタリングで制限できると良いだろう。ペアレンタルコントロールは、フィルタリングのほか端末の各種機能を制限する仕組みもあり、時間制限、課金禁止、アプリのダウンロード制限などができるため、有害コンテンツをきっかけとしたトラブル防止のためにも、フィルタリングと併せて利用してほしい。
ポイント
有害な画像や動画、問題のある広告など、子供に見せたくないコンテンツがインターネット上にはたくさんあり、見る側で防ぐ対策をすることが大切である。フィルタリングなどのペアレンタルコントロールのほか、広告をブロックする機能・設定を利用する方法もある。インターネットに接続できる端末は、スマートフォン、タブレット、PC、ゲーム機、音楽プレーヤー、テレビと増えており、機能や設定もそれぞれであるため、子供に使わせる端末でどのような制限ができるのかよく知っておくと良いだろう。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。