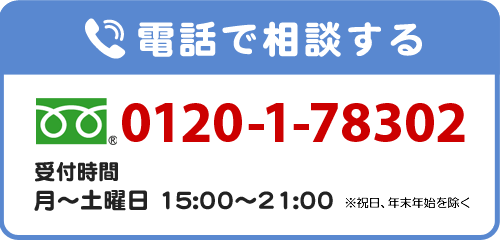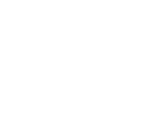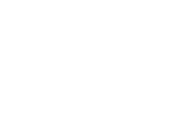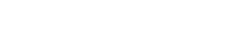相談事例
料金関係
相談内容(2025年10月・青少年女子)
スマートフォンで課金をしすぎてしまった。自分が勝手に課金したから悪いのは自分だと思うが、家族から責められて辛い。
アドバイス
民法で定められている「未成年者契約の取消し」について最寄りの消費生活センターへ相談してほしい。相談の際はいつ、いくら、どこに、どのような契約をしたのかなどをそろえておくことでスムーズな相談につながるだろう。今後は同じことが繰り返されないように、スマートフォンの利用ルールについて家族と話し合えると良い。今はお互いがヒートアップした状況かもしれないので、冷静になってから再度話し合うことを勧める。
ポイント
民法では、未成年者が法律行為をする場合には、法定代理人(保護者)の同意が必要であり、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができると決められている。しかし取り消しが適用されるかどうかはケースバイケースであり、家庭で対策をしっかり考えておくことも大切である。例として、機能制限(ペアレンタルコントロール機能)を活用し課金ができないようにしたり、課金の際は保護者の許諾を必要とする方法がある。携帯電話会社によっては、料金が一定金額を超えるとアラートが保護者に届いたり、設定した金額以上の課金ができないプランもあるため活用してほしい。
相談内容(2025年5月・青少年男子の保護者)
保護者の知らないうちに子供がオンラインゲームで課金をしてしまい、クレジットカード払いで引き落とされていた。スマートフォンは保護者が使わなくなった古い端末だが、アカウント設定は保護者のままだった。一部は返金申請が認められたのだが、残りの返金について知りたい。
アドバイス
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合に、「未成年者取り消し権」によって契約を取り消すことができると決められている。契約を取り消して返金をしてもらうためには満たさなければいけない要件があり、クレジットカード会社やゲーム会社などとの交渉も必要になるため、詳しくは最寄りの消費生活センターへ相談することを勧める。相談の際は、課金したアプリの名前、日時、金額などを詳しく時系列のメモにまとめ、購入履歴もチェックして引き落とされた金額と一致していることを確認しておくと良い。今後の再発防止のために、家庭でルールを作ることやフィルタリングやペアレンタルコントロール(機能制限)を利用すると良いだろう。
ポイント
保護者が使わなくなったスマートフォンを子供に使わせるときに気を付けたいのが課金トラブルだが、しっかり対策することで防ぐことができる。フィルタリングの利用、アプリ購入の制限、子供のアカウントでの正しい年齢設定などを確認しておくと良い。端末を初期化することも有効である。機械的な設定のほかに、親子で課金の仕組みやお金の使い方について話し合うことも大事である。
相談内容(2024年10月・青少年男子の保護者)
子供が保護者の就寝中にスマートフォンのロックを勝手に解除し、ゲームで課金をしたことがわかった。金額が高額なのでどのように注意したら良いか悩んでいる。
アドバイス
課金について話をするときには、家庭での約束事やルールと照らし合わせて、何が守られていなかったのかを整理しながら話し合えると良いだろう。たとえば保護者のスマートフォンのロックを勝手に解除したことがルール違反であった場合は、なぜ守られなかったのか、本人の話をよく聞いてほしい。なお、民法では「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められている。適用されるかどうかはゲーム会社等の判断になると思われるが、返金について最寄りの消費者生活センターへ相談することを勧める。
ポイント
ゲーム課金は保護者が知らないうちに高額になっていることが多いが、未然防止のためにできることもたくさんある。スマートフォンにクレジットカード情報を残さないこと、課金ができないように制限すること、利用履歴や購入履歴をこまめに確認するなどが対策になるだろう。オンライン上で課金をすると現実のお金の支払いがどうなるのかを、家族全員で話し合って知識を共有することが大切である。
相談内容(2024年5月・青少年女子の保護者)
子供がスマートフォンのデータ通信量(ギガ数)をオートチャージに変更してしまい、契約者である保護者に高額な請求が届いた。携帯電話会社に問い合わせたが請求金額は変えられないとのことだった。気づくのが遅れたのだが、全額支払わなければいけないのか。
アドバイス
民法では、未成年者が契約などの法律行為をする場合には、法定代理人(保護者)の同意が必要であり、「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められている。適用されるかどうかは携帯電話事業者の判断になると思われるが、この未成年者取消権の相談をするのが良いだろう。手続きについて詳しくは、最寄りの消費者生活センターへ、契約者本人から相談することを勧める。
ポイント
SNSやゲーム、動画視聴などでデータ通信量(ギガ数)を使い切ってしまったときに、この事例のようにオートチャージ機能が設定されていると、自動的に一定量のデータが追加され、チャージが何度も繰り返されると高額になってしまう。オートチャージ機能の設定や追加チャージの申し込みは、一般的には携帯電話会社などのホームページ上の契約者ページを通じてできることが多く、子供でも簡単にできてしまう。このため、予想外のトラブル防止のためには、契約者ページに子供がアクセスできないように制限しておくことが望ましい。
相談内容(2023年12月・青少年女子の保護者)
娘が保護者のクレジットカードを勝手に持ち出して、スマートフォンで課金や買い物をしていた。ゲーム、漫画、フリマアプリでの支払いに使ったことがわかっている。フィルタリングを利用しているがすぐに解除してしまう。
アドバイス
民法では、未成年者が契約などの法律行為をする場合には、法定代理人(保護者)の同意が必要であり、「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められている。契約を取り消すには満たさなければいけない要件があり、クレジットカード会社やアプリの会社などとの交渉も必要になる。詳しくは最寄りの消費生活センターへ相談することを勧める。相談の際には、課金や買い物をしたアプリの名前、日時、金額の明細を詳しく時系列のメモにまとめ、購入履歴もチェックして請求金額と一致していることを確認しておくと良い。
ポイント
インターネット上では子供でも簡単にクレジットカード決済ができてしまうが、原則として本人以外が使うことは、カード会社の利用規約で禁止されている。このため、子供が勝手に保護者のカードを使うことも、規約違反と見なされてペナルティが生じる可能性があることを親子で話し合えると良い。子供がルールを守れるようにフィルタリングや機能制限(課金禁止設定など)を利用することが有効だが、そのパスワードを勝手に解除されないようにしっかり管理することも大切である。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。