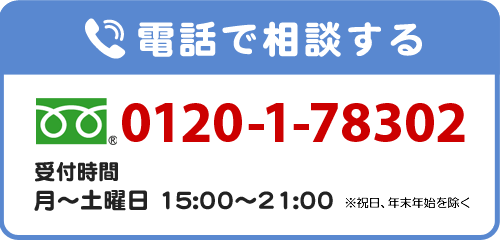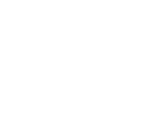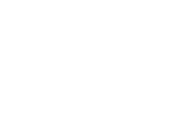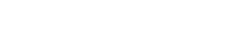相談事例
料金関係
相談内容(2018年2月・青少年女子の保護者)
子供がスマホで課金をしていた。携帯電話会社からの請求で判明した。利用したのは2つのアプリ。フィルタリングを利用しているが、その2つのアプリの利用は認めていた。しかし課金は許可しないように設定したはずである。子供は課金について認めたが、自然に課金できてしまい疑問を持たなかったとのこと。課金の操作をしようとしても、キャリア決済の画面にたどり着くまでにパスワードを入力する必要があるが、子供に確認すると、パスワードは聞かれなかったとのこと。このようなことが起こるのか。支払いは拒否できないのか。
アドバイス
パスワードの入力なしでは一般に考えれば決済までは到達しないと思われるので、スマホに一度入力したパスワードが保存されていた可能性もある。未成年者であり保護者が同意をしていない買い物であることから、支払い義務については、民法では未成年者契約の取り消しという措置がある。その措置が適用されるためには、いくつかの条件があり、たとえば、親の承諾を得ていないことや、契約時に年齢などの虚偽がないことや、保護者の管理状況などで判断されるだろう。利用したアイテムの提供元や決済会社との交渉次第になると思われる。交渉に当たっては消費生活センターへ相談して支援を得ることを勧める。
ポイント
なぜ課金ができてしまったのかは、今後のために検証が必要だが、機械的に制御しても、子供自身で解除ができる場合もあれば、機械に記憶されている場合もある。このため、機械に頼る対策だけでなく、今後のためにもインターネットの利用についてルールを決め、インターネットで提供されているサービスには利用料金が必要なサービスもたくさんあること、画面上の記載をよく読むこと、新しいサービスを利用する際には保護者の同意を必ず得ることなど、子供自身に利用に関する自覚を持たせることも必要だろう。
相談内容(2017年11月・青少年女子の保護者)
子供がゲームで課金をしていた。クレジットカードの利用明細はインターネット上で確認するようになっており、引き落とし予定を確認すると数十万円もあった。子供に確認すると、課金をしていることを告白した。どうにかならないだろうか。
アドバイス
未成年者契約の取り消しという措置がある。ただしすべての契約が取り消しになるのではなく、クレジットカードの管理など保護者の責務が問われるかもしれない。ケースバイケースなので、クレジットカードの明細、何のゲームでどこの運営会社かなどを調べて、消費生活センターへ相談することを勧める。ゲーム運営会社によっては、青少年の使い過ぎを防ぐため、上限の金額を決めている。その場合は青少年が利用していることがゲーム運営会社に伝わっていないといけないので、利用年齢の設定によっては、上限を超えてしまうこともあり得る。ゲーム運営会社との交渉についても消費生活センターに相談すると良い。
ポイント
オンラインゲームの課金には、クレジットカード番号やパスワードの入力が必要だが、入力さえできてしまえば、子供だけでも高額の課金ができてしまう。この点は保護者が十分な知識を身につけておいてほしい。子供が利用する端末にはクレジットカード番号や有料サービスへのパスワードを保存しないこと、課金が生じたときの通知は保護者のメールアドレス宛てに届くように設定するなど、トラブル防止の対策はたくさんある。そして何より大事なことは、子供がインターネットをどのように利用しているのかを親子でコミュニケーションをとりながら把握し、見守ることだろう。
相談内容(2017年8月・青少年女子の保護者)
娘がスマホのオンラインゲームで課金していたことが、クレジットカード会社からのいくつかの請求で発覚した。利用明細書には高額の課金があり、クレジットカード会社から確認の連絡もあった。娘に聞くと、保護者や家族のクレジットカード番号を勝手に使った事実を話してくれた。ロックをかけていない家族のスマホを勝手に使っていたようだ。
アドバイス
未成年者が保護者の同意を得ずに有料サービスを利用した場合には、契約を取り消すこともできる。ただし、保護者のカード管理責任やゲームの利用状況などから判断され、必ず契約を取り消せるわけではない。具体的な対応について、消費生活センターに相談することを勧める。クレジットカード会社へも状況をお話しした方が良い。今後のために、課金に関する家庭の約束事を定めると良いだろう。家族については、スマホにロックをかけること、暗証番号は時々変える、生年月日のような推測されやすい番号にしないことを注意してほしい。
ポイント
保護者の知らないところで子供がクレジットカード決済で課金をしてしまうトラブルは、高額であることも多くダメージが大きい。インターネット上ではカードそのものを提示するわけではなく、カード番号と暗証番号の組み合わせで決済ができてしまう。子供が勝手に課金したことを証明するのも難しい。このような特徴を、保護者はしっかりと理解しておく必要がある。子供がオンラインゲームを利用している家庭では、無料ゲームであっても、課金の仕組みや料金体系について親子で確認し、使い方についても十分に話し合い、約束事を定めることが不可欠だろう。年齢を登録する場合は、必ず子供の実年齢を登録するなど、利用規約を守ることも徹底してほしい。
相談内容(2017年1月・青少年男子の保護者)
息子が家族の携帯電話を無断で使ったらしく、その携帯電話にパケット通信料金超過のメールが届いた。驚いて調べてみたら、息子が携帯電話でテレビを視聴したことが分かった。携帯電話は通話のみの契約であり、パケット通信料定額制の契約ではない。どうしたら良いだろうか。料金を支払わなければいけないのか。
アドバイス
携帯電話のテレビを試聴していることから、何らかのサイトを開いたりデータ放送を利用した結果、パケット通信料金が発生したのかもしれない。早急に携帯電話会社へ相談に行くことを勧める。未成年者契約の取り消しが適用されるかどうかについて相談すると良いだろう。家族の携帯電話の管理状況を確認し、パケット通信料金が発生する仕組みなども家庭で話し合ってほしい。
ポイント
民法では「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」としている。今回、その適用に関する可否について、居住地の消費生活センターに相談することも可能だろう。未成年者契約でも、その状況によっては取り消せない場合があることも理解しておく必要があるだろう。またトラブル再発に向けて、子供自身がインターネットを利用する際に、何が有料で何が無料かを、保護者と一緒に予め確認しておくことも重要である。そして基本的なマナーだが、自分の持ち物ではない物を利用する時には、その持ち主から必ず承諾を得ることも忘れてはならない。
相談内容(2016年12月・青少年女子の保護者)
音楽プレーヤーを利用し、親の知らないうちに多数の音楽ダウンロードを行い高額な料金が発生していることが分かった。音楽ダウンロードに使ったIDは、保護者が数年前に取得し、クレジットカード情報を登録する必要があり入力したものだった。無料ゲームのゲーム内課金は出来ないように設定していたが、保護者がプリペイドカードに入金してアプリのスタンプを購入したときの手順やパスワードを娘が隣で見ていて、覚えていたらしい。娘が勝手にプリペイドカードに入金したようだった。
アドバイス
最寄の消費者生活センターへの相談を勧める。音楽の提供元、クレジットカード会社との交渉次第だが、未成年者が法定代理人である親の同意がないままに音楽ダウンロードやゲーム課金等の利用契約を行った場合、民法の観点から原則として契約を取り消すことができる可能性はあるだろう。ただし保護者のカード管理責任なども判断され、必ず契約を取り消せるわけではない。今後は同様のトラブルを起こさないように、親子で使い方のルールを話し合ってほしい。
ポイント
保護者名義のクレジットカードを知らないうちに子供が使って課金してしまったトラブルである。音楽プレーヤーであっても、本格的にインターネットに接続でき、有料の音楽をダウンロードすれば料金が発生することを保護者も認識しておく必要がある。子供がインターネット上でどのようなサービスを利用しているのか、それが有料なのか無料なのか、有料ならば課金が発生する時点はどこなのか等を、保護者は子供と一緒に確認し、管理する必要があるだろう。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。