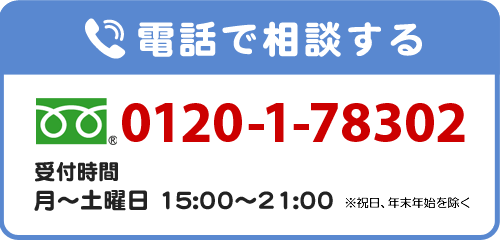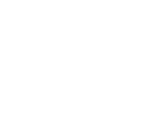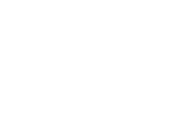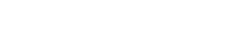相談事例
ネットいじめ
相談内容(2016年9月・青少年女子の保護者)
SNSのグループトークで、娘が仲が悪くなった友達の個人情報を投稿してしまい、相手の保護者が学校と警察に連絡した。相手の希望は投稿を削除してほしいということだが、娘はSNSグループに書き込んだことで恐くなり、SNSアカウントを削除してしまったため、内容を確認できない。グループ内の何人かの友達に削除してほしいと伝え、数人は消したと言い、削除した後の画面コピーを送ってきた人もいた。グループ全体を削除したり、少しでも拡散を止める方法はあるのだろうか。
アドバイス
SNSのグループ全体を削除することは難しいと思われ、グループ内メンバーへ削除をお願いする方法を考えることになる。本人はアカウントを削除しているため、グループ内で連絡を取れる人を通じて削除依頼をグループ内に伝える方法があるだろう。その際には、個人情報を書き込んだことを深く反省していること、二度と同じような過ちを繰り返さないことを、グループ内のメンバーに伝えてもらうようにする。グループ内メンバーから書き込みが消えたとしても、その周囲へ広がっている可能性もゼロではないが、今できる対策はグループ内の各メンバーに削除をお願いすることだろう。
ポイント
学校で友人関係が悪化した理由から、前後の見境なくSNSに悪口を書き込んで起きたトラブルである。一時的な気持ちからだったとしても、書き込んだ内容を完全に消すことが本当に難しいことを理解して、同じような過ちを二度と起こさないように注意してほしい。もし相手と直接会えるならば、反省している気持ちを直接伝えることも解決方法の一つだろう。
相談内容(2016年7月・青少年男子の保護者)
子供が動画サイトに投稿している画像について、行き違いがあり、個人名や誹謗中傷のコメントが書かれるようになった。書いているのは、最近知り合った他校の生徒である。現在は相手をブロックし、コメントを削除することで対応している。他に手立てはあるか。
アドバイス
機械的にできる対策は、現在行っているブロック、コメントの削除、動画サイトの運営側に報告することだろう。サイトのヘルプページに報告機能の説明と注意点が書かれているのでよく読むと良い。コメントに対して過剰に反応していると収拾がつかなくなることもあるので、本人に悪いところがなかったとしても、淡々と削除をしていくことが一番良いだろう。削除することにも疲れてしまうのであれば、一旦動画サイトのアカウントを削除したり、動画を削除することも対処法の1つだろう。
ポイント
自分が投稿したものに対しての誹謗中傷は、受け入れ難いことだが、この事例のように、ユーザーのブロックや、コメントの削除などの機能がサイトにあれば、それらを利用することが現実的な対処である。インターネット上にはさまざまな価値観を持った利用者が集まり、お互いに顔が見えないため誤解が生じやすい。さまざまな反応もインターネットに情報を発信することのリスクだと考えて受け流すことも対策の1つかもしれない。リスクを考慮しても発信したい内容なのかをよく考えることも必要である。
相談内容(2016年5月・青少年男子)
SNSでトラブルがあり、しばらくSNSから離れた。その後、トラブルの相手をブロックし、再開したときに「ブロックしたおかげで整理ができて良かった」という投稿をした。この文章は他人が書いた文章をコピーをして自分の投稿としてしまった。その後、トラブルのあった相手が、その文章が自分に向けられた発信と誤解をしたようで、SNSを休業してしまった。自分は名誉棄損で訴えられたりしないだろうか。
アドバイス
他人の投稿を無断で利用するなど、ルールを無視した行動については自身の行動に責任がある。また、名誉棄損で訴えられるかを心配するのではなく、誤解を与えるような行動をしたことについて、マイナスな投稿を読んだ相手の立場に立って考えてほしい。たとえば、しばらくSNSはやらない、再開する時にはルールを守った行動をする等、自分ができることを考えてほしい。
ポイント
言葉だけのコミュニケーションは大変難しく、自分の投稿を読んだ相手がその内容を100%理解できるとは限らない。人にはそれぞれ価値観があり、その違いもある。その時の感情をそのまま投稿するのではなく、投稿する必要がある内容なのかを考えてから投稿してほしい。自分が発信した情報は自分に責任があることを忘れてはならない。マイナスな感情の投稿は見ている方も気持ち良いものではないので、インターネットという公共の場所でのマナーを心がけてほしい。
相談内容(2016年3月・青少年男子の保護者)
あるサイトで他人が制作した画像を無許可でコピーして投稿したことで、第三者から批判されてしまった。名前と共に謝罪を要求する投稿が出され、それに同調する人もいる。またたくまに広まり炎上してしまった。サイトのルールでは、他人の画像をコピーするときには本人に許可をとることになっている。この点は反省し、サイトからはこれまでの画像を削除し、しばらく利用しないことにした。
アドバイス
作品には著作権があるので、一般的には、他人の著作物を無断で利用することはルール違反である。今回のことで、著作権のことを親子で理解し、同じ失敗を繰り返さないようにすることが一番大事なことである。今は一時的に炎上してしまったが、ネット上の批判は時間がたてば収まることもあるので、このまま静観することを勧める。学校でもいじめが起こるようなことがあれば、現実生活での対処をするべきなので、先生に相談しておくことを勧める。
ポイント
炎上のきっかけとなったのは、他人の著作物を許可なく利用してしまったことであり、今回の経験を勉強の機会として活かせると良い。インターネット上には、他人の行動をチェックし、炎上の機会をうかがっている利用者も存在する。不特定多数によるいじめ行為をエスカレートさせないために、インターネット上ではしばらく静観していることが選択肢の1つである。しかし、その影響が学校生活に及ぶケースもあり、そのような場合は学校の協力も得て、現実の世界を安心して過ごすための対処も不可欠だろう。
相談内容(2016年3月・青少年女子)
悪ふざけで、他人を中傷する嘘の書き込みをSNSに書いてしまった。すると、その書き込みが知れ渡り、悪口を言われ炎上してしまった。自分のSNSアカウントや過去の書き込みも悪口と共に広められた。迷惑なメッセージもたくさん送られてくる。怖くなってSNSを非公開設定にすると、見えるようにするためのリクエストが送られてきた。良くない書き込みをしたのが悪いのだが、たくさんの人に悪口をたくさん書かれてとても辛い。
アドバイス
インターネットは公共の場であり情報の発信には責任が問われることを認識してほしい。今できることとしては、静観して様子を見る、アカウントを消す、公開設定に戻して謝罪文を投稿するなどの選択肢が考えられる。現実に起きていること、SNSで起きていること、相手との関係性など様々な要因を総合的に考えて対応する必要があるだろう。インターネット上だけでなく現実生活での問題になるので、学校の先生や身近にいる大人にも相談してほしい。もしも個人が特定できるような情報がSNSを含め、インターネットに書かれている場合には、削除の手続きを進める方法がある。
ポイント
インターネットに他人の悪口を書くことは、現実社会で他人の悪口を言いふらすことと同じである。しかも、書いた悪口は、必ずしも簡単に消せるわけではない。誰かによってコピーされるのを防ぐことも難しい。気軽に情報発信ができるインターネット上であっても、現実社会と同じようにルールとマナーを守り、発信した言葉に責任を持つことが求められている。
※ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じようなトラブルであっても、個々の状況が異なるため、解決内容もそれに従い違ってきます。